消化器外科 砂川 秀樹 インタビュー
低侵襲手術と万全の連携体制で、安全かつ確実な治療を


消化器外科副部長
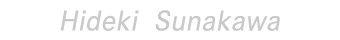
研修を通じて消化器外科に惹かれた
現在、私は新東京病院でヘルニアセンター長および消化器外科副部長を務めています。これまで消化器外科の診療を中心に、患者さんの身体への負担をできるだけ少なくする腹腔鏡手術やロボット手術といった低侵襲手術の技術を習得し、経験を積んできました。現在はこれらの技術を用いて、安全かつ質の高い手術を実施すると同時に、後輩医師の育成にも力を入れています。
私は沖縄県の宮古島で生まれ育ちました。幼い頃から医師になりたいという夢を持っていましたが、進路として本格的に意識するようになったのは、兄の影響が大きかったと思います。兄は私が小学生の頃にはすでに医学部に在籍しており、身近な存在として医療の道を選んだ姿が、自分の将来を考えるうえでひとつのきっかけになりました。
高校卒業後は愛媛大学医学部へ進学しました。学生時代から外科医に憧れを抱いていましたが、専門領域を明確に定めてはいませんでした。消化器外科医を志すようになったきっかけは、初期研修を受けた愛媛県立中央病院での経験です。さまざまな診療科を回る中で、消化器外科の手術や治療に触れ、その魅力とやりがいを強く感じました。
腹腔鏡・ロボット手術の技術を磨く
初期研修終了後は、松山赤十字病院で消化器外科の後期研修を受け、本格的に消化器外科医としてのキャリアを歩み始めました。さらに専門性を深めるため、自らの希望で千葉県柏市の国立がん研究センター東病院に移りました。当時の松山では胃の腹腔鏡手術が導入されたばかりであり、自分自身が十分な経験を積む必要性を感じていたためです。国立がん研究センター東病院では腹腔鏡手術の権威である木下敬弘先生の指導を受け、5年間の研鑽を積み、内視鏡外科技術認定医の資格を取得しました。

2018年、新東京病院で消化器外科を新たに立ち上げる計画があると聞き、そのビジョンに共感し移籍しました。当院は低侵襲手術を軸に診療を展開する方針で、ロボット手術の導入も視野に入れていました。ロボット手術システム「da Vinci」が導入されると同時に資格を取得し、現在はその指導医(プロクター)資格も有しています。
安全な治療と後進の育成に取り組む
当院の消化器外科は、「上部消化管チーム」「下部消化管チーム」「肝胆膵チーム」の3つのチームで構成されています。私はその中の上部消化管チームに所属し、部長の岡部寛先生とともに常勤のメンバーとして診療や指導を担当しています。他の医師は定期的なローテーションにより各チームを経験し、多様な知識と技術を身につけることができる柔軟な体制を整えています。
ヘルニア診療については、特定のチームだけではなく、全てのチームが手術に携わっています。各チームには私のような指導的立場の医師が配置されており、若手医師が確実に手術技術を習得できるように教育体制を整えています。これにより、手術の質を保ちながら次世代への技術継承にも注力しています。
チームで支える診療体制
当院のヘルニアセンターでは、鼠径部(そけいぶ)ヘルニア、一般に「脱腸」と呼ばれる病気を中心に、おへそ周りの臍(さい)ヘルニア、手術後の傷跡から内臓が出てしまう瘢痕(はんこん)ヘルニアなど、お腹のさまざまな部分で起こるヘルニアに対して幅広く診療を行っています。「ヘルニア」とは、本来あるべき場所から臓器や脂肪が飛び出してしまう状態のことで、自然に治ることはほとんどありません。そのため、根本的に治すには手術が必要です。

鼠径ヘルニアは放置しておくと、腸の一部が脱出したまま戻らなくなる「嵌頓(かんとん)」という状態になることがあり、最悪の場合、腸の血流が途絶えて壊死に至る危険性もあります。そのため、たとえ症状が軽く見えても、診断された時点で手術を検討することが大切です。
体への負担を抑え、早期回復をめざす
当センターの特徴は、患者さんの身体への負担をできるだけ軽くした腹腔鏡手術を積極的に行っていることです。腹腔鏡手術とは、小さな穴を数か所だけ開けて細いカメラや器具を使って行う手術で、傷が小さく済むため、術後の痛みが少なく回復も早くなります。
当院では、メッシュ(人工の補強剤)を使ってヘルニアの穴をふさぐ腹腔鏡手術を主に行っていますが、患者さん一人ひとりの体調や病状に合わせて最適な治療法を提案しています。手術の時間は60分前後で、術後3時間ほどで歩行や食事が可能になります。入院期間も1~2日と短いため、仕事や生活にあまり影響を与えずに治療が受けられます。また、日帰り手術にも対応しています。
手術実績をもとに専門的な診療を行う
鼠径部に違和感や腫れを感じた際、「泌尿器科を受診すべきか」と悩まれる患者さんも少なくありません。しかし、鼠径ヘルニアは泌尿器科ではなく消化器外科の専門領域であるため、適切な治療につながるまでに時間を要することがあります。当院のヘルニアセンターでは、こうした患者さんが適切な診療・治療を迅速に受けられるような体制を整備しています。当センターでは年間約160〜170件の手術を行っており、これは虫垂炎や胆嚢摘出手術を超える件数であり、患者さんのニーズが高い領域であることを示しています。

ヘルニア外来を開設し、最適な治療を提案
現在は毎週月曜日に「ヘルニア外来」を設けており、診察から治療方針の決定、手術のご案内まで、しっかりと対応させていただいています。外来では、ふくらみの状態、痛みの有無、日常生活への影響、手術の必要性などを総合的に判断し、ご本人やご家族と相談しながら治療の方向性を決めていきます。
当院では、腹腔鏡手術を基本としながらも、年齢や健康状態に応じた柔軟な治療選択肢を提案しています。今後、保険制度の整備が進めば、より進化した手術法としてロボット支援手術の導入も検討していく予定です(※現在、ヘルニア手術においてはロボット支援手術は保険適用外となっています)。
鼠径ヘルニアは早期の外科的対応が重要
地域のかかりつけ医の先生方には、鼠径ヘルニアが疑われる、あるいは診断後の治療方針に迷われる患者さんがいらした際、ぜひ当院へご紹介いただければと願っております。「小さいから」「痛みがないから」と判断されがちなケースでも、潜在的リスクが存在するため、外科的な評価が重要です。
受診先がわからないという患者さんのお声を聞くたびに、我々の情報発信がより一層必要であると感じています。鼠径ヘルニアは決して珍しい疾患ではなく、適切な治療方法も明確に確立されています。私たちは患者さんが安心して最適なタイミングで手術を受けられるよう、常に万全の準備を整えています。

今後はロボット手術の活用を含め、さらに質の高いヘルニア診療を目指し、診療体制の強化や情報発信にも取り組んでまいります。地域の皆さまや先生方とともに、患者さんが安心して医療につながれる環境をつくっていきたいと考えています。
