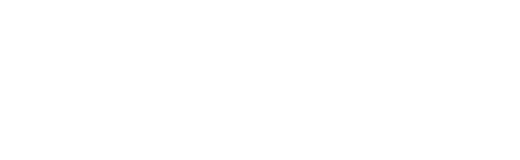心臓内科 長沼 亨 インタビュー


心臓内科部長 兼
SHD治療部長 兼
データ管理・臨床研究センター長
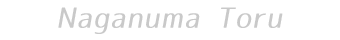
心筋梗塞を患った祖父の担当医との出会いが転機に
もともと、医学生時代はスポーツ医学(整形外科)に興味を持っていました。ちょうど私が医師になった2004年に、大学卒業後の2年間はいろいろな科をローテーションして研修する初期臨床研修制度が始まりました。地元広島の公立病院で研修させていただきながら、次第に循環器内科に惹かれていきました。その大きなきっかけは、私の幼少期に祖父の心筋梗塞を治療してくださった循環器内科の指導医との出会いでした。驚いたことに、その先生は臨床検査技師であった私の父とも以前同じ病院で働いていたことがあり、何か縁を感じました。また、実際に病院で研修を進める中で、循環器内科の医師が多岐にわたるスキルを持ち、診断から治療まで一貫して行える点に強い魅力を感じました。
診断から治療まで一貫した診療が魅力
循環器内科の魅力は、自分で診断し治療まで完結できることです。自分の手で患者さんを助けることができる診療に大きなやりがいを感じました。以前勤めていた病院には、若手とベテラン医師がペアを組み、「全科当直」として急患に対応するシステムがありました。その中で、循環器内科医が頼りにされる場面が多い印象を受けました。私たちはある程度の外科処置もでき、麻酔・救急科のように蘇生処置も行えます。一方、もちろんやむを得ないのですが、眼科や耳鼻科の先生たちは普段そういった診療を行わないので、急患への対応が難しいケースもありました。

また研修医2年目で精神科を研修中に、突然自分の目の前で抗精神薬による薬剤性QT延長が原因でTdP(心室頻拍)を発症し、病棟で急変した症例を経験しました。上級医が来るまで、冷や汗をかきながらマスク換気など蘇生処置を行ったことを今でも鮮明に覚えています。この経験で循環器内科にさらに興味を持つようになりました。このような上司との縁や経験がなかったら、外科系に進んでいたかもしれません。
カテーテル治療に注力
後期研修(卒後3-5年目)を終える頃には、次のステップとしてカテーテル治療に力を入れている病院で学びたいと考えるようになりました。通常、医師のキャリアパスでは大学の医局に所属しその人事に従うのが一般的です。しかし、私はその道は選ばず、自分の力で挑戦するというある意味リスクのある選択をしました。医師としてのキャリアが不安定になる可能性もありましたが、成功すれば大きな飛躍が期待できるものでした。幸運にも、当時の上司が「お前は広島を出て世界を見てきなさい」と応援してくれたことで、広島を離れ新しいステージに進むことができました。2009年に当院に入職してからは、冠動脈カテーテル治療の権威である前院長の中村淳先生の指導を受けました。さらに、2012年から2014年まで、イタリアのミラノにあるSan Raffaele Scientific Instituteの心臓カテーテル治療の世界的権威であるAntonio Colombo先生のもとに留学する機会を得ました。
世界的権威のもとで得た経験
イタリアでの留学期間中は、Colombo先生のもとで学術的な活動に専念しました。当初は、他の多くの留学医と同様に、結果を出せずに苦しんでいました。最初の3か月で体重が3キロ落ちるほどストレスが大きかったことを覚えています。Colombo先生はさまざまな心臓カテーテル治療に精通され、特に冠動脈分岐部ステント治療についてはそのほとんどのテクニックが彼によって考案されたものでした。当時術者の間では第一選択とされていながらまとまったデータが無かったTAPというテクニックについての論文(The long-term clinical outcome of T-stenting and small protrusion technique for coronary bifurcation lesions. JACC Cardiovasc Interv. 2013; 6: 554-61.)が有名な雑誌に掲載されたことが、私にとって大きな転機となりました。

Colombo先生も大変喜んでくださり、留学して半年ほど経った頃、初めて「Toru」と名前で呼んでくださるようになり、それからは次々と課題が与えられるようになりました。それまでは日本人留学生はまとめて「Japanese boys!」と呼ばれることもありましたが、今となっては懐かしい思い出です。その課題に応えることで、徐々に自分のポジションを確立していくことができました。また、Colombo先生と一緒にハートチームの責任者であった心臓外科医Ottavio Afrieri先生からも刺激を受けました。彼が考案した外科的な僧帽弁治療法であるAlfieri stitchをもとにして、その後、経皮的僧帽弁接合不全修復術が開発されたことは私たちの分野ではよく知られた話です。2014年に帰国後、構造的心臓病(Structural Heart Disease: SHD)に対する低侵襲カテーテル治療の責任者を任せていただくことになりました。
構造的心臓病(SHD)
SHDに対する低侵襲カテーテル治療には、大動脈弁狭窄症に対する大動脈弁植え込み術(Transcatheter Aortic Valve Implantation: TAVI)、僧帽弁逆流症に対する僧帽弁接合不全修復術(Transcatheter Edge-to-Edge Repair: TEER)、二次孔型心房中隔欠損症に対する閉鎖術、脳梗塞の予防治療である卵円孔開存閉鎖術や左心耳閉鎖術(Left Atrial Appendage Closure: LAAC)などがあり、当院は豊富な経験を有しています。弁膜症の症状としては、胸の痛みや圧迫感、息切れ、動悸、むくみ、体重増加、失神などが挙げられます。これらの疾患は、当初は自覚症状がない方も少なくありません。健診で心雑音が聴こえたり、レントゲンや心電図で異常が見つかったりすることで疾患が判明するケースもあります。

高齢者にも負担が少ない、心臓病治療の選択肢
SHDの治療法には大きく分けて2つの方法があります。ひとつは、胸を切らずに行う低侵襲なカテーテル治療で、もうひとつは、胸部を開いて直接病変にアプローチする外科治療です。カテーテル治療は、細長いカテーテルという道具を使って血管内から行うため、患者さんの身体への負担が少ないのが最大の特徴です。傷が小さいので出血や創部感染のリスクが低く、術後の早期離床や早期退院が可能になります。
地域と連携した先端医療の提供を目指す
2013年12月に千葉県では初のTAVI認定施設として治療を開始しました。麻酔科のサポート下に局所麻酔、大腿動脈穿刺法で行う超低侵襲TAVIについて、日本ではかなり早い段階から始めています。世界の最先端の施設にも負けない実績があり、以前から積極的に取り組んできたことが当院の強みです。病診連携の面では今後さらに強化が必要だと感じています。TAVIをはじめとするSHD治療は専門性の高い分野であり、患者さんや地域の医療機関に正しく理解してもらうことが大切です。今後は地域のクリニックや病院との連携を深め、必要な治療を早期に提供できる体制を整えていきたいと考えています。国内外でのプレゼンスを高めながら、また地域の患者さんに貢献できる医療機関として、さらなる成長を目指しています。